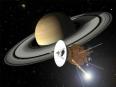
うちゅうたんさき【宇宙探査機】
月・惑星の探査および宇宙空間を航行しながら観測などを行い、観測データを地上に送る宇宙航行体。探査衛星。
うちゅうちゅうけい【宇宙中継】
地球を回る軌道に打ち上げた人工衛星を利用して中継し、遠距離へ放送電波を送る方式。また、その方式によるテレビ中継や番組。

うちゅうつうしん【宇宙通信】
人工衛星に設置した無線局を中継点として送受信する電波通信。人工衛星などと地上との間、宇宙船相互間の通信で行われる。特に地上の二点間で行われる通信は衛星通信ともいう。
うちゅうデブリ【宇宙デブリ】
⇒スペースデブリ
うちゅうのちへいせん【宇宙の地平線】
膨張する宇宙における事象の地平線。観測者から遠ざかる速度が光速を超えている領域との境界面であり、原理的に観測可能な最も遠方の境界面といえる。この境界を越えた領域からの光(電磁波)や重力波は、永遠に観測者の元に届くことはない。宇宙の地平面。→宇宙の地平線問題
うちゅうのちへいせんもんだい【宇宙の地平線問題】
宇宙背景放射が方向によらず一様であるという観測事実と膨張宇宙論との間にある矛盾。膨張する宇宙において宇宙の地平線を越えた二つの領域は物理的な相関をもたない。にもかかわらず、宇宙背景放射は地平線の大きさ(現在の天球面の角度にして約2度)を越えて一様であり、すなわち、どの領域も同じ物理状態にある。この矛盾は宇宙の地平線問題と呼ばれ、宇宙論における議論の対象となっていた。インフレーション宇宙論によると、宇宙創成のごく初期に物理的相関があった小領域が地平線を越えて急激に膨張したと仮定することで、この矛盾を解決すると考えられている。地平線問題。
うちゅうのちへいめん【宇宙の地平面】
⇒宇宙の地平線
うちゅうのはれあがり【宇宙の晴(れ)上(が)り】
ビッグバン以来、膨張を続ける宇宙の歴史において、電磁波が初めて自由に伝播できるようになった時期、またはその現象。超高温・高密度の状態で始まった宇宙は膨張に伴い平均温度が下がり、約3000〜4000ケルビンになった時、電離していた原子核と電子が再結合し、それまで電子に散乱されていた光(電磁波)が初めて長距離を進めるようになった。これを霧が晴れて視界が利くようになった様子になぞらえ、「晴れ上がり」とよぶ。宇宙が始まって約38万年後のことと考えられる。宇宙背景放射は、この晴れ上がりにより自由に伝播できるようになった黒体放射が、宇宙膨張による赤方偏移を受けて波長が伸びたものである。
うちゅうはいけいほうしゃ【宇宙背景放射】
宇宙のあらゆる方向から同じ強度で入射してくる、絶対温度が約3ケルビンの黒体放射に相当する電波。1965年に米国のA=A=ペンジアスとR=W=ウィルソンが発見。ビッグバン、およびインフレーション宇宙論を支持する観測的な証拠であると考えられている。宇宙背景輻射。宇宙黒体放射。宇宙マイクロ波背景放射。3K放射。3K背景放射。3K黒体放射。CMB(cosmic microwave background radiation)。CBR(cosmic background radiation)。
うちゅうはなび【宇宙花火】
平成19年(2007)9月2日夜、打ち上げたロケットから放出されたリチウムが、太陽の光を受けて赤く輝いた現象を花火にたとえたもの。宇宙航空研究開発機構(JAXA)が各大学と共同で高層大気観測のために行った実験による。