ニュースヘッドライン注目の記事
-
新浪氏会見で浮上した「3つの矛盾」1時間前

-
清水容疑者の逮捕 俳優兄の対応注目1時間前

-
部員1人遠征先に置き去り 顧問指示7時間前

-
藤本美貴 2つの意外な資格を告白2時間前

-
清水容疑者 前日に「逮捕情報」3時間前

-
JUMP 中島裕翔卒業の深刻な余波1時間前

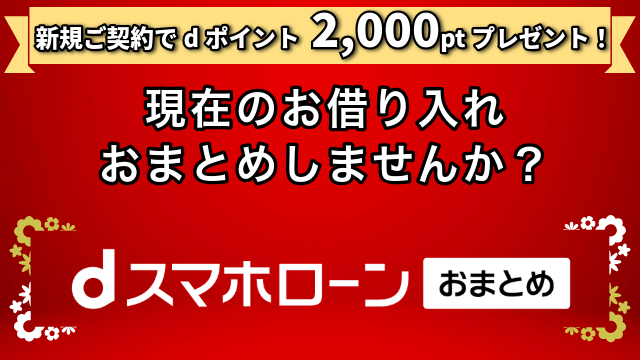
PR dスマホローン

PR OCN
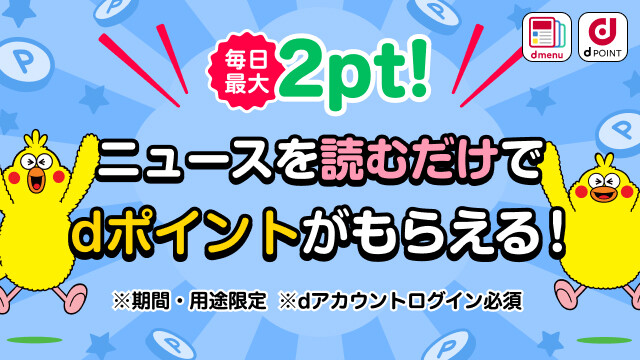
PR dmenuニュース














